その作品を読む前から、有栖川有栖、という変わった名前は知っていた。
図書館の文庫棚に収まって、魅惑的なタイトルがこちらに謎をかけてきていたからだ。『海のある奈良に死す』、『月光ゲーム』、『ロシア紅茶の謎』―タイトルの言葉の選び方からして、あれはたぶん推理小説だ。そこには、月光の下で開く白い花のような、美しく残酷な物語が書かれているに違いないのだ。賭けてもいい、私はあれが絶対に好きだ。
私は、自分の身長では手の届かない上段の棚を眺めながら、推理作家「有栖川有栖さん」について考えた。私の想像の中で、髪の長い、青いワンピースに真珠のネックレスをつけた女性が、スフィンクスの笑みを浮かべた。
……著者についてのそんな(勝手な)想像は、その後ほどなくして、児童書架にあった有栖川有栖著『虹果て村の秘密』の「あとがき」によって見事に裏切られた。やられたぜ有栖川有栖。髪が長いのは合ってたよ。
作品への想像は、裏切られなかった。
有栖川有栖が書く謎は美しくて残酷だ。そして物語を動かしているのは、その残酷さのほうだ。
この物語では誰よりもまず、犯人自身が、自分の残酷さを直視できない。だから「鍵を掛ける」のだ。事故に見せかけるのも、嫌疑をかぶせるのも、ふざけたふうを装うのも、全部自分を守るためだ。「自分の信じる自分」を守るために、彼らはいわば鍵を掛けて閉じこもる。
それを開けられる者が―探偵がいるとすれば、犯人以上の力で、残酷さを見ることのできる者だろう。物語の探偵、火村英生曰く、
「人を裁けるのは人だけです。神なんかじゃない。」
有栖川有栖著『46番目の密室』新装版文庫p.86よりセリフ一部抜粋
有栖川有栖の推理小説はそうして成立する。
図書館の棚に手の届くようになった私は、火村英生と有栖川有栖の後をついて歩き、たくさんの鍵の掛かった部屋、鍵の掛かった人々を訪れることになった。
推理小説の大家、真壁聖一の別荘でのクリスマスパーティーに、小説家や編集者たちが招かれた。駆出しの推理小説家、有栖川有栖(アリス)は友人の犯罪学者、火村英生を伴って参加する。しかし、一夜明けて、館の主は悲惨な死をとげて発見された。明らかな他殺の状態だが、現場は密室だった。まるで、彼の得意とした密室トリックのように。

(イラストは上が火村、下がアリス。画材は今回もホルベイン透明水彩と、一部カラーインクです)
これが有栖川有栖の、通称「作家アリスシリーズ」の第1作目だ。1992年初刊となる。
ここから始まっている。
その後の有栖川作品を読んで『46番目』に戻ってくると、完成されてるなあ、と思うと同時に、ここから始まっている、とも思う。精緻なトリックと端正な解法が与える一種のドライさは有栖川有栖の持ち味で、これはデビュー作から変わらない。けれど、私は火村の人となりや真壁の最期にも惹きつけられてしまう。そもそも有栖川有栖作品が好きな人で、抒情的な魅力を語らないものは、およそいない。これはのちに有栖川作品を貫くもう一つの軸になっていく。(このシリーズの近刊『鍵の掛かった男』を読むと、うわーここまできたか、これは90年代の有栖川有栖には書けないなひえー、と思うのだ)
火村とアリスはこの後も数々の不幸な終わりに出会う。人生における幸せの得がたさを見る。
単なる探偵コンビものというには、彼らのまなざしはいろいろなものを見すぎていて、これは煉獄を巡るような物語だ。残酷さに目を閉じてはいけない。閉じた扉を前に立ちすくんではいけない。そのメッセージは物語を超えてこちらに問いかける。人を裁けるのは……
【関連記事】
◆『46番目の密室』作中で流れるグレン・グールドのゴールドベルク変奏曲について。
◆ほかの有栖川有栖作品

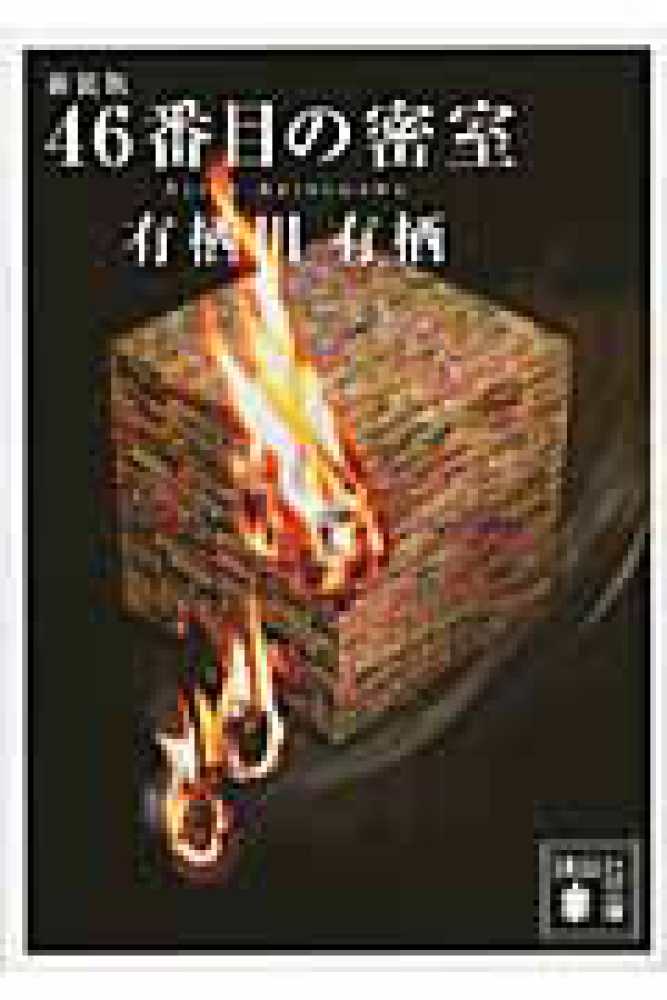





コメント