「恩田陸の本って中盤までは最高におもしろいのに、すっきり終わらないんだもんなあ」
友人は楽器の練習をしながら言った。夕暮れの教室で彼女は大きな弦楽器をゴオゴオ弾き、私は傍らで机に浅く腰かけていた。メトロノームに合わせて、弦楽器はさっきから同じフレーズを繰り返していた。弓がいったりきたりした。
「『六番目の小夜子』もさあ、終わったかどうかわかんないような終わり方じゃん」
彼女の言うことも否定できない。私は、試しに『小夜子』がすっきり終わった場合のストーリーを考えた。恩田陸のほかの作品、『麦の海に沈む果実』や『蛇行する川のほとり』のように、少女のいちどきりの物語として完璧な終わり方をした『小夜子』を。
いや、それじゃだめだ。物語が色褪せてしまうなんてものではない。それはもう『小夜子』ではない。
「私、『小夜子』が好きだし、あの終わり方もいいと思うよ。あれでなくちゃいけないような気がする……」
「そうかなあ」
納得しない友人は、ますます弦をゴオゴオ鳴らした。また同じフレーズに戻った。
私はこのとき、すっきり終わらないことこそが『小夜子』をほかの学園青春ものから区別していると感じた。ただ、それをうまく言葉にできなかった。
それから私は折に触れては『小夜子』を読み返した。大人になって読むことで、よく見えてきたものがあり、いくらかは言葉にできそうだ。
『六番目の小夜子』では、読み手の意識はたえず物語の「いま」と「伝説」の間を往復する。そう仕掛けられている。登場人物たちのいちどきりの青春が、総数のなかのひとつでしかないことを何度も確認させられる。そういう点で学園小説としては異色であり、もう一歩踏み込んで言えば、これは学園小説という枠を超えて読むことができる作品だ。現代の私たちが前提としている時間のイメージ、「直線的に進む時間」への、ひとつの根強いカウンターとして読めるかもしれない。
そう読んでみようと思うのだ。
「あなたがカバンを置いたその机」「あなたが今座って頬杖をついている机」「あなたが居眠りをしている机」「その机はずっと同じ場所にあって」「一年前も」「そのまた前の年も」「あなたと同じ歳の誰かが」「その場所に座っていた」「頬杖をついていた」「居眠りをしていた」
恩田陸著『六番目の小夜子』文庫版p.169より
その高校には伝説があった。3年に一度、生徒の中から「サヨコ」が選ばれるという。選ばれた者は始業式に赤い花を活け、学園祭で劇を上演する。この伝説は決しておおやけにしてはいけない。すべては暗黙の了解のもと、生徒たちによって脈々と執り行われてきた。そして六番目のサヨコの年である春、津村沙世子という名の、美しく謎めいた少女がやってきた。
反復される事象の中で、その一回だけが特別であるとき、物語を物語ることはたやすい。森鷗外の『高瀬舟』も、渡し守である庄兵衛の乗せた罪人が今日はたまたま「これまで類のない、珍らしい罪人」だったことによる。あるいはアニメ“魔法少女まどか☆マギカ”でもいい。何度も繰り返される試行のなかで、その一回きりの試行が歴史を変えてしまったとき、物語られる価値は自然と生じる。
加えて、自ら新しい事象を作り出した人間だけを真に創造的とする近代以降の価値観がある。「歴史に残る」という言い回しに表されるように、直線的に進む時間は傑物や偉業を求める。現代社会で主人公になるなら、金輪際現れない♪エポックメイキングかつオンリーワンであるべし、なのだ。
言い換えれば、特別な事象もしくは特別な人間は、現代において物語を作りやすい。
この物語も一見、特別な人間が引き起こす特別な事象に見える。転入生の津村沙世子は、だれもかれも彼女から目が離せないほどの美少女で、しかも抜群の秀才である。彼女が「サヨコ伝説」を背景に学校中をかき回していくストーリーは謎と期待の連続となる。今年は二人いるらしい「サヨコ」。津村沙世子は今年の「サヨコ」なのか。彼女は何者で、何を知っているのか。「サヨコ伝説」は成功するのか。おおやけにしてはいけないはずの「サヨコ伝説」の謎に迫るもう一人の秀才、関根秋は津村沙世子の正体を明らかにすることができるのか。
しかし一方で、もし相当に冷静な目で読むなら、『六番目の小夜子』の1年間はほかの5回と比べて明らかに特異とは言えない。つまりこれは一見『高瀬舟』型の物語のようでいて、そうではないのだ。この高校は「六番目」に匹敵するほどのストーリーをすでに複数もっている(なんてこった)。作中では生徒によって「サヨコ伝説」の歴史が語られるのだが、「一番目」はオリジナルであり謎に包まれ、「二番目」の選ばれし「サヨコ」は非業の死を遂げたらしい。「サヨコ伝説」が制度化された「三番目」にも事情がありそうだ。それに「サヨコ伝説」を解明しようとする者も初めてではない。それぞれの年がおそらくドラマティックであったのだ。
沙世子や秋たちのきらめく「いま」を描きながら、一方で「サヨコ伝説」について繰り返し言及することで、物語はしきりに「いま」を「何回かあるうちの一回でしかない」と主張する。『六番目の小夜子』というタイトルもその主張のひとつと読める。

特別ではない。あるいは、どの回も特別であるがゆえに、その特別さが際立たない。
津村沙世子には超自然的な力があるようにも見えるが、中盤まで読むとそのイメージは一貫しなくなる。意外と普通の女の子だ。この高校なら数年に一度くらいはこのような人材が入ってきてもおかしくはない。また、「サヨコ伝説」には調整役がいないでもないのだが、すべての原因をこの人物に求めても、説明できない部分が残る[1](それが読後すっきりしない理由のひとつでもある)。
これは特定の個人に起因する特別な物語ではないのだ。
別の視点が必要だ。
「それでまた、皆が望んだのさ、『サヨコ』が現れるのを」
同p.41より
『六番目の小夜子』に流れるもうひとつの時間に注目する。直線的に進み創造的な人物を求める現代の時間、ではないもの。
宗教学者のエリアーデは世界中の神話と祭儀を研究し、古代人の意識について考察した。古代人の時間は円環として表現される。神話を再現する祭儀を行うことで、現実の時間は神話の時間に回帰し、また宇宙開闢のエネルギーが現実の時間に吹き込まれる。それを繰り返す古代人の意識のなかで、真に一回きりの事象も、真に最終的な変化もない[2]。優れた個人が現れたら、神話や伝説の人物に投影すればいい。あれはきっと英雄ギルガメシュの生まれ変わりじゃよ。
生徒たちは、3年前という自分たちの在籍しない時間を神話として、いわば祭儀をしている。「サヨコ伝説」はおまじないの形としては、あまりに祭儀だ。新学期にそなえられる花はなぜ黄色や白ではなく「赤い花」でなくてはいけないのか。それが犠牲の血の色だから。なぜ木に吊るすのは赤いてるてる坊主なのだろうか。このかわいらしい人形が生贄の形態を残しているから。そういった形だけではない。彼らの目的もまずひとつは「天意を問う」ことであり、まさに、亀甲を焼いて収穫の多寡を占った古代の王国人のようなおこないだ。
(文化祭のシーンで流れる“ジムノペディ”は、文庫版解説の岡田幸四郎も指摘しているように、フランスの作曲家、エリック・サティが古代ギリシアの祭りから着想した曲だ[3]。岡田はそこから永劫回帰のイメージを採った。私もそう思う。)
なるほど、これは古代の祭儀なのだ。
それなら、なにをおいてでも遂行しなければないのがわかる。「天意を問う」のは暗黙ながらまだ理解された目的で、彼らが自分たちでさえ気づいていない目的が、まだある。
地上を流れる時間は、神話を再現する祭儀によって、たえず若く更新されなければならない。地上のあらゆる出来事を神話の繰り返しとする。太陽のもと新しき何物もなし。それでいいのだ。それで、彼らは(私たちは)元気で生きていける。まったく誰にも生きられたことのない未知の時間を生きていけるほど、彼らは(私たちは)強くはない。人間は、これほどまでに伝説を―物語を必要とする。
全校生徒の共同幻想として受け継がれる「サヨコ伝説」は、決して過去にならない、円環の時間の上にある。物語終盤のアクシデントで「サヨコ」は存続の危機に陥ったように見えるが、その実、これが到底傷つくはずもない。皆が、生きるために「サヨコ」を望んでいるのだから。めまいがするようなラストのモノローグも、読み手はどこかで、こうなるはずだったと思うのではないか。
直線的に進む時間を表面的には受け入れながら、円環の時間を捨てきれない。21世紀に入ってもなお、二つの時間のなかで矛盾しながら生きる私たちに、『六番目の小夜子』は懐かしい顔をした友人として立ち現れる。何度でも。
冒頭に戻る。
転入したばかりの津村沙世子が、赤いチューリップを抱えた「もうひとりのサヨコ」に言う。「あなたも赤い花を活けに来たの?」。通常の会話であれば、事実の確認、もしくは軽い驚きを伝えるものとして発せられるだろう。
しかしいまや、このセリフは、たまたま沙世子の口を借りた、物語自体から発せられた声として聞こえる。かつて学校にいた、何千という顔の見えない生徒たちが口を揃えて言う。私たちは犠牲を払った。私たちは祈ってきた。そして、喜ばしいことに、この円環の時間に新しく招かれたあなたも―
「あなたも赤い花を活けに来たの?」
同p.18より、太字は著者による
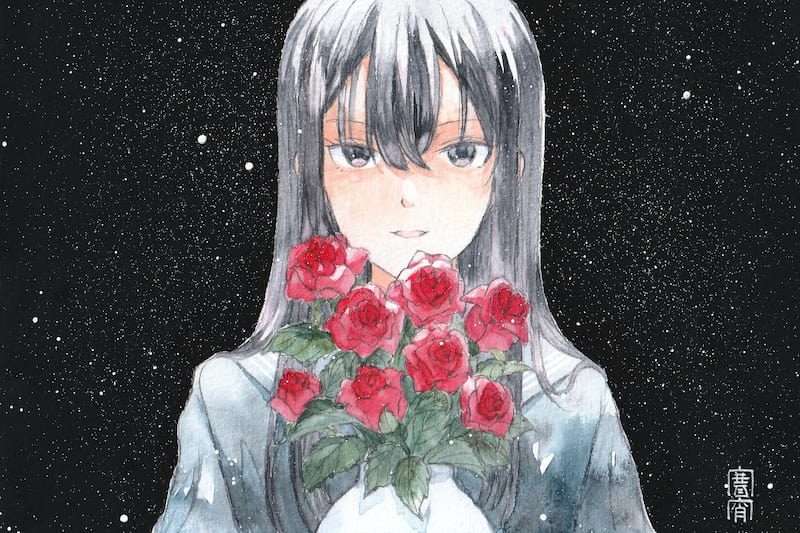
【参考】
[1]中川智寛、恩田陸「六番目の小夜子」論 : 小夜子とは誰なのか、東海学園言語・文学・文化 21、2023年9月、p.77-84
→「サヨコ伝説」における「調整役」の関与していない部分がはっきり指摘されている。論じ方によってはもっと挙がると思う。たとえばサヨコ伝説の年表を書いてみると挙がる。この論文はwebで閲覧できる(2026年1月現在)。作品を読んだ人向け。
[2]ミルチャ・エリアーデ『永遠回帰の神話 祖型と反復』未来社1963年
[3]ジャン=ジョエル・バルビエ『サティとピアノで』リブロポート1993年、p.40-46
→岡田は文庫解説でエリック・サティのジムノペディを「古代の祭りの絵を描いた壺を見て作曲したと言われる」としている。私もそのエピソードはライナーノーツかなにかで見た記憶があるのだけど、壺に描かれていた絵が由来かどうかは、今回調べきれなかった。ただ、サティがつけた「ジムノペディ(Gymnopédies)」という曲名が、アポロン神を讃えるスパルタの祭りでの青少年の踊り「グムノパイディアイ」のフランス語訳であることは[3]ほか複数の文献が指摘している。結論として、この曲から祭儀による永劫回帰のイメージを採るのは充分可能と判断した。
【関連記事】
◆ほかの恩田陸作品







コメント