学園もの小説をよく読みます。登場人物たちと年が近かった頃も読みましたが、大人になってからもまだ読んでいます。これからも読むつもりです。特に、息苦しい雰囲気の学園が出てくるのをたくさん読んでいます。
ある時、学園もの小説について「厳しい校則とか閉鎖的な人間関係とかさ、そういうのが読みごたえがあるんだよねえー」と言ったら、同窓の友人から「自分は開放的な学校でいいかげんに楽しくやっておいて、勝手なことを言う」と笑われました。その通りです。私たちがいたのは教室にホットプレートを持ち込んでパンケーキを焼くようなクラスでした。厳しい校則?閉鎖的な人間関係?なにそれ。
その場では一緒に笑ってしまったけれど、ときどき、このときの会話を思い出します。
不思議です。
なぜ、私は「閉鎖的な学園もの」を、しかも大人になってまで、読んでいるのでしょう。自分の学校生活を重ねて共感しているのではない。これは私が通らなかった道のはずです。それに、エンターテイメントとして楽しむのに、わざわざ息苦しくつらい設定のものを探して読まなくたっていいのに。
でも、ちょっとまって。それなら「閉鎖的な学園もの」がこんなにたくさん出版されてこの世に存在するはずない。だって、世の中の大半の人は閉鎖的でない学校に通って、もちろん苦悩のあまり宿舎を脱走したり失踪したり刺したり刺されたりせず、社会に出てきてるわけです。そのうえでつらい学園ものを読んでいるのです。私と同じように。
「閉鎖的な学園もの」は時代を問わず、結構あります。「閉鎖的な学園もの」をおおざっぱに「学園が一般常識からみてもかなり生徒の自由を制限する(制限が多岐にわたるかピンポイントで重大かは問わない)」と捉えなおして考えてみます。ちなみに先ほどの「閉鎖的な人間関係」のほうは、学園がそんな風にして生徒にストレスをかけていれば自然に発生してくるので個別に考えなくてもよさそうでした……(やれやれ)。
ちょっと思いつくだけでもヴェデキント『ミネハハ』、プロイスラー『クラバート』、宮木あや子『雨の塔』、長野まゆみ『テレヴィジョン・シティ』、恩田陸『麦の海に沈む果実』、綾辻行人『緋色の囁き』、石野晶『月のさなぎ』、小森香折『二コルの塔』、篠田真由美『屍の園』、森深紅『アクエリアム』、カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』などなど。ヘッセ『車輪の下』には現代の一般常識はあてはめられないにしても、書き手が「閉鎖的な学園こんちくしょう」と思って書いているのがポイントなのでここに入れてもいいでしょう。ヘッセ本人も神学校を中退しています。
並べてみるとわかります。
これらの閉鎖的な学園は、「学園を出ていく勇気ある生徒」とセットです。途中の学年で脱出する話もありますし、最終学年まで志を曲げずにいて、無事卒業する話もあります。
それなのです、たぶん。
皆が(少なくとも私が)本当に読みたいのは、「勇気ある個人が、凝り固まった共同体が導くのとは違う答えを出す物語」なのではないでしょうか。決別する、とまではいかないにしても。
そしてそう読むとき、学園もの小説は、学園の枠を超えるのではないでしょうか。
読み手が現実に闘うものはそれぞれあるでしょう。その対象があまりにリアルに描かれると、読むだけで打ちひしがれてしまうかもしれない。なによりフィクションの力が働かない。しかし、それが「学園」として描かれた場合、ワンクッションおいて、箱庭を眺めるような俯瞰した視界が現れてきます。ものを考えさせないこういう組織は現実にもあるな、とか。こういう裏切り方するやついるよ、とか。少し冷静になって、単純化した(それゆえに本質的な)物語として受け止められる。そういう視界を立ち上げることが、フィクションとしての「閉鎖的な学園もの」の役割なのだと思います。
そうして箱庭から持ち帰った勇気がつもりつもって、やがて、読み手を息のできる場所へ連れていきます。どの物語も、きっと、そう願って書かれたのです。
◆閉鎖的な学園から脱出する物語セレクション◆
①『二コルの塔』(小森香折著)
厳しい修道院学校で刺繍を学んでいた少女、二コルは、学校の秘密を知り、魔法を解いて外へ出ていく。修道院と外の世界を自在に行き来することのできるシダでできた猫、サルヴァドールの活躍は大きいです。越境者の言葉に耳を傾けること。身ぶりをまねてみること。

②『アクエリアム』(森深紅著)
学園の生徒に秘密裏に割り振られた「管理番号」を発見した二人の少女は、その謎を解こうとする。不穏で、独特の美しさを持つ青春推理小説です。観察し、仮説を立て、実験して立証するやりかたで、世界を正しく把握すること。でもこの話、その代償がとても重いんだなあ……。

③『クラバート』(オトフリート・プロイスラー著)
身寄りのない少年が森の奥の水車場に導かれ、恐ろしい親方に言われるままに職人として働く。水車場は魔法を教える学校だった。やがて仲間を味方につけ、村の少女の助けを得て、少年は親方と対峙する。これは最後、魔法でなんとかするとみせて、魔法が効かなくなる場面がすごいのです。結局、魔法じゃない。

④『テレヴィジョン・シティ』(長野まゆみ著)
≪生徒≫と呼ばれる少年たちは巨大なビルディングの中で、システムの管理下に置かれて暮らしている。外の世界を知らない。本当にあるのかさえも分からない「碧い惑星」にむけて、二人の少年が脱出を図る。システムの管理を攪乱する≪クロス≫と呼ばれる操作が、何の隠喩なのか、いろいろ考えられますが、私は、本を読むことにも似ていると思います。ないはずの記憶を取り込んで、予測できない変異を起こすこと。
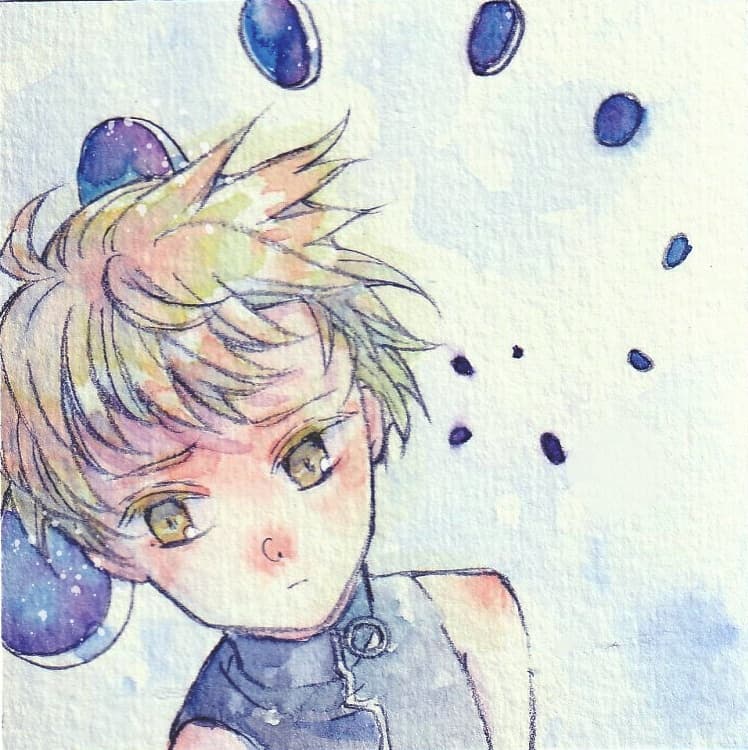







コメント